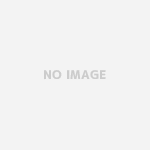久々に骨太の書籍を読んだ。そして現実の国際政治を動かす要因としての説明としてはとても説得力があるものと感じた。これまではリベラル色の強い、それこそ学生時代は猪口氏の「戦争と平和」みたいなものによる腹落ちのしない、そして戦争がなくならない現実が続くことにもやもやとしていたものがあった。このオフェンシブリアリズム、そもそも国際社会がアナーキーであり、大国は力による安全を求める、しかし相手の考えを100%わからない、等はこの50年間の不良であった視界を明るくしてくれたような気がする。そして中国の台頭とそれへの米国の動きも2001年に書いたものとは思われない不気味さがあり、今後さらにこの理論に基づく米中関係が進展していくかと思うととても暗い気持ちになる。
「大国政治の悲劇」ジョン・J・ミアシャイマー(2024年2月25日)
投稿日:
執筆者:nobumori